会計
決算書は承認?報告?
Tweet株主総会の季節になりました。
日本の多くの会社は3月決算ですが、会社法その他の規定により、株主総会を決算日から3ヶ月以内に開かなければなりません。そのため、6月は株主総会シーズンとして知られています。
株式を持っている方は、この時期に株主総会招集通知を受け取られた方もいらっしゃるでしょう。
さて、多くの招集通知、特に上場会社では、決算書は「報告」となっています。
一方、知り合いや親戚の会社の株式を持っている、とか、相続した株式がある場合などで、特に上場していない会社などからは、招集通知で決算書の「承認」を求められることがあります。
この、決算書の「報告」と「承認」とは、一体どんな違いがあるのでしょうか。
そもそも株式会社は株主のもので、その所有権を記したものが株式です。
株主は、日頃の経営には口出ししない代わり、一年の事業の内容を総点検し、それによって経営者である取締役に引き続き経営をやってもらうのか、それともクビにするのか、などを全て株主総会で決めます。
従って、総決算である決算書を株主総会で承認する、というのは株主にとって当然のこと、ということになります。
しかし、現代のように会社の業務内容が複雑になり、そして会計の方も諸制度が導入されて複雑になると、決算書を見せられて承認してください、というのは一般の株主には難しくなってきます。
そこで、一定規模の会社については、決算書が適正に作られているか専門家に判断してもらい、問題がなければ株主へは報告で充分だろう、ということになりました。
これが公認会計士(または監査法人)による会計監査制度です。会社法439条にその規定がありますが、制度自体は旧商法から続いているものです。
さて、公認会計士の監査を受けない場合には、決算書は株主総会で承認、ということになりますが、既に出来上がってしまった決算書を承認しない、ということはあり得るのでしょうか。
決算は過去の出来事を数字に起こしたものだから、承認するもしないも、変えようがないような気もします。
実は、会計というものは、事実に基づいて記録される部分と、見積もりによって記録される部分とで成り立っています。
事実に基づいて記録される部分というのは、例えば現金で支出した費用とか、現金で受け取った売上とか、通常は金額が決まっており変わりようがない部分です。
(IFRSでは、たとえ現金で受け取った売上でもその通りに記録しないこともあるのですが、それはまた別の機会に述べます)
一方、見積もりによる部分というのは、必ずしも現金によって支出したり受け取ったりしていなくても、その事業年度に起こったことを何らかの基準に基づいて記録するものです。
例えば、減価償却費などがこれに相当します。購入した固定資産の値段というものは決まっていますが、それを何年で減価償却するか、ということは企業がその使用年数を判断して決めることになっています。
(日本では、慣行的に税法が定める法定耐用年数を用いることが多いです)
将来起こりうる損失をある程度見込んで計上する、という会計制度もあります。何々引当金、と呼ばれるものがそうです。また、最近導入された「資産除去債務」という会計制度もこれに当たります。
筆者は、株主総会で決算書が承認されなかった例というのは見たことがありませんが、例えば次のような事例が考えられるでしょう。
比較的業績が好調だったので、経営者は従業員に決算賞与で報いたいと思い、決算に盛り込みます。
(実際に支給するのは決算の後であっても、従業員の頑張りはその事業年度にあったものですから、その事業年度の決算に見込計上します)。
他方、株主は従業員に賞与を支給するのではなく、その分を利益として配当に回してほしい、と思うかもしれません。そこで、決算書を承認せず、賞与の部分を取り下げるよう経営者に要求する、ということが一つの例として考えられるでしょう。
あるいは、経営者の作成した決算書がどうにも信用できない、ということであれば、株主は決算書を承認せず、決算のやり直しを命じるかもしれません。
承認した決算書に基づいて、配当をどうするか決めるのも株主総会の重要な事項です。配当は会社の財産を還元するという、株主の大事な権利の一つですので、そのもとになる決算書を承認する、というのも株主の重要な権利であるわけです。
年金はどうして企業の業績に影響を与えるのか(その2)-確定拠出年金
Tweet前回は、企業の決算に大きな影響を与える可能性のある確定給付年金と年金会計の関係について説明しました。
今回は、その影響を回避する確定拠出年金についてご説明します。
確定拠出年金は、その名のとおり、企業からの「拠出額」が「確定」している年金です。
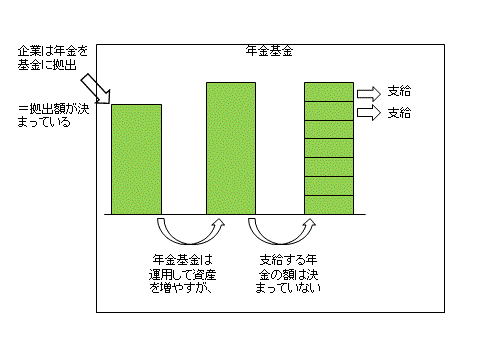
企業からの拠出額が確定しているので、その後の運用や、給付額の確定については企業は責任を負いません。
この点が、「給付額」が「確定」している確定給付年金と全く異なるところです。
また、企業の責任は年金の拠出に限られていることから、年金会計の上でも、拠出した時点で費用として計上するだけで済み、決算への影響が少ないという特徴があります。
このため、外資系企業では、年金会計から生じる業績への影響懸念から、確定給付年金をやめて確定拠出年金へ移行する企業も多くありました。
企業会計の上からはメリットのある確定拠出年金ですが、年金資産の運用上のリスクや、運用成績そのものの良しあしのリスクが消えてしまったわけではありません。
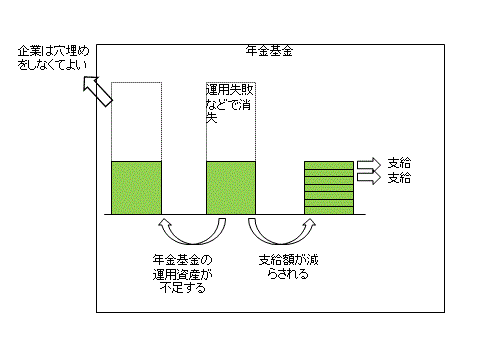
運用成績が良くなければ、それは年金支給額の減額、という形で受給者に跳ね返ってきます。
したがって、どのような資産運用をするかは、年金受給者が自分で決めることになっています。この点が、運用自体は全て年金基金に任せる確定給付年金と異なるところです。
したがって、年金受給者自身が投資運用に高い関心を持ち、責任を持って運用することが求められます。
我が国では、「お金に関すること」に高い関心を持つことはどちらかというと「守銭奴」「金に汚い」とされ、否定的なイメージがありました。
その一方で、任せきりだった年金運用では、AIJのような事件が起きたり、年金会計によって企業そのものの業績に大きな影響を与えるケースも出てきています。
自分の年金は自分で考える確定拠出年金は、必然的に「お金に対する関心」を高めざるをえない効果も含まれているようです。
また、確定拠出年金は導入されてまだ年数もあまり経たないことから、税務上のメリットもあまり大きくありません。
閣僚会議の「成長ファイナンス推進会議」における、確定拠出年金を拡充する方針も、もう少し確定拠出年金の制度上の魅力を高めて、確定給付年金からの移行を進めようという意図が感じられます。
年金はどうして企業の業績に影響を与えるのか(その1)-確定給付年金
Tweet年金はどうして企業の業績に影響を与えるのか。年金会計の仕組みを簡単に解説します。
2012年5月8日付日経新聞に、政府は閣僚会議の「成長ファイナンス推進会議」において、確定拠出年金を拡充する方針を打ち出したとありました。
先のAIJ事件における企業年金の消失問題など、年金に関する話題は途切れることがありません。
年金は企業の業績も揺るがす大問題と言われますが、一体何が問題なのでしょうか。
企業が支払う年金というのは、いわば退職金の後払いのようなものです。
退職金制度のある会社では、定年退職を迎えると、退職金が支払われますが、これを一度に受け取るのではなく、退職後の一定の期間、受け取るようにすることができます。これが企業年金と言われるものです。
この受け取り方には、確定給付型と確定拠出型の二つの種類があります。
確定給付型というのは、ずっと昔から採用されていた方法で、多くの企業がこれに基づいて年金を支給しています。
年金が毎月決まった金額受け取れる、すなわち「給付額」が「確定」していることから、確定給付年金と言われます。
もともと年金は退職金の分割後払いなのだから、毎月決まった金額を受け取れて当り前だろう、と思いますが、ことはそう簡単ではありません。
後払いされる年金は、企業が預かるのではなく、年金基金といういわばファンドが預かっています。
企業は決まった金額を年金基金に支払い(これを拠出といいます)、基金はそれを元手に運用します。そして、運用で得た投資利益も含めた金額を受給者(元従業員)に年金として支給します。
この支給額が「確定給付額」となっているわけです。
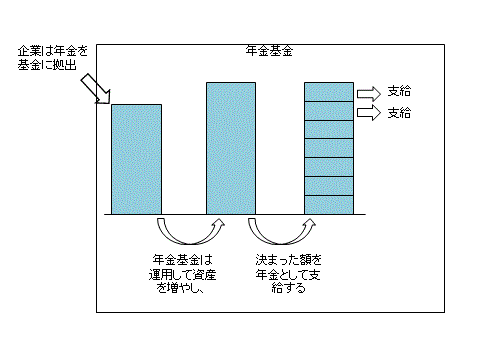
支給額が確定しているということは、その元手になる投資運用もある程度確定している必要があるわけですが、残念ながら昨今の投資環境の悪化から、予定した投資運用ができていない基金が大半と言われています。
そうなると、給付額は一定ですから、基金は過去から積み立てた余裕も取り崩して年金を支払わなければならないことになります。
AIJの事件は、投資運用が低迷して、予定した運用が行えなくなった基金が、一発逆転を狙って運用成績の良かったAIJに乗り換えたことから発生しています。
実際には予定していた運用が行えていなかったどころか、元本を大幅に下回ってしまったわけですから、預かり資産も大幅に小さくなってしまった年金基金も数多くあります。
いずれは年金を支払わなければならない、かつその給付額は一定しているわけですから、資産が大幅に小さくなっているといずれ基金は破たんします。
このとき生じた年金基金の穴埋めは、まず一義的にはその給付元の企業が行わなければならないことになっています。
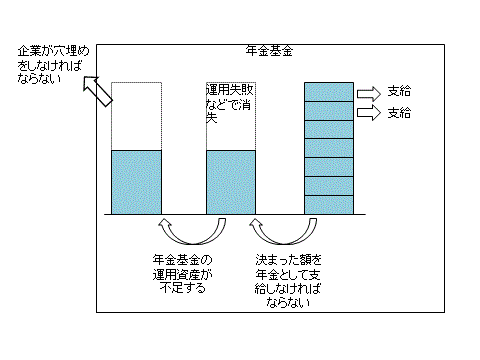
この穴埋めが突然やってくると、企業の業績は大きくぶれて、大きな影響を与えます。そこで、毎決算期ごとに、企業年金の財政状態を調べ、穴埋めしなければならないとしたら幾ら必要か、を算定し、それを一定の基準で決算に反映させなければならないことになっています。これが、「年金会計」と呼ばれるものです。
ただ、この年金会計は、全ての企業に義務付けられているものではなく、多くは上場会社や大企業に限られます。
中小企業の多くはこの年金会計を採用しておらず、したがってあるとき年金基金から多額の穴埋めを依頼され、たちまち業績が悪化してしまう危険を抱える会社も少なくありません。
このような影響を回避するために導入されたのが確定拠出年金です。
これについては、次回ご紹介します。
ソニーの業績修正-繰延税金資産とは
Tweet2012年4月10日、ソニーは2011年の業績について、2月に立てた業績予想よりも3千億円悪化することを発表しました。
発表資料によれば、米国などにおける繰延税金資産に対し評価性引当金を計上することなどにより、追加の税金費用約3,000億円を計上することになった、とあります。
これほど大きな影響を与える繰延税金資産とは何でしょうか。
当事務所の別ブログでは、繰延税金資産について簡単に解説しています。
繰延税金資産とは要するに、以前に生じた損失の税金相当分を将来に繰り延べることです。
日本には繰越欠損という制度があります。所得上、赤字が生じた年度は税金を払う必要がありませんが、その損失を繰り延べることができ、将来に利益が生じたときに払う税金をそれで賄うことができる制度です。
米国にも同様の制度があります。
報道資料では、繰延税金資産の回収可能性を評価するにあたり数年間にわたる累積損失は重要なマイナス要因とみなされる、とあります。
つまり、過去に繰り延べた欠損金は、将来に利益が生じたときに払う税金で賄うわけですが、将来に生じるであろう利益が少なければ、賄いきれなくなる可能性があるわけです。
繰延税金資産を計上した時は、将来の利益で賄えることが前提となっています。しかし、後々の事業環境の変化によって、将来の利益の予測に変化が生じ、賄いきれなくなると、その分は取り戻せない税金ということで、資産を取り崩す必要が出てきます。
日本、米国をはじめ多くの会計原則では、その評価を毎回行うことを要求しています。
ソニーも、2月の業績発表時は問題なし、と考えられていたものが、数か月経って精査したところ、賄いきれなくなった、という判断になったものと思われます。
マスコミでは、今回の業績修正と繰延税金資産に対する評価の引き当てによる大幅赤字を報道しています。
しかし筆者は、今回の引き当てによる業績悪化よりも、もっと深刻な問題が潜在的にあることを危惧しています。
評価の引き当ては将来の利益で賄いきれなくなったことを意味し、すなわち、将来の利益の見通しが下がったことを意味するからです。
日本の電機メーカーの凋落が巷で語られていますが、暗くなってしまった将来の見通しを何とか引き上げられるよう、頑張ってもらいたいものです。
「減損」とは
Tweet前社長の解任問題でオリンパスが連日話題になっています。
当初は単なる社内コミュニケーションによるものとされていましたが、過去に行われたM&Aの買収価格の問題も浮上し、議論が噴出しているようです。
このM&A案件では、買収してまもなく、リーマンショックによって「のれん」について減損を適用することになったと説明されています。
前回は、その「のれん」について解説しましたが、一方、この「減損」とは何でしょうか。
時を同じく、パナソニックもTV事業で「減損」を行い、1千億円を超える損失を計上すると発表しています。
「減損」とは、文字通り、持っている資産を「減じる」ことによって生じる「損失」のことです。
工場の建物や機械などの資産は、購入した後にその使用期間に合わせて減価償却を行っていきます。
事業が順調な時は、この減価償却をまかなって十分な利益が出ているはずです。
しかし、事業が不調になると、事業の赤字が続き、将来もどうにもなりそうもない、という状況もあり得ます。
このとき、工場の建物や機械などの資産は、引き続き減価償却を行っていくわけですが、この先減価償却を続けても利益がでないとすると、そもそも資産としての価値がないのではないか、という話が出てきます。
現代のように経営環境がめまぐるしく変わる中では、そういう資産を長く置いておいても価値が上がることはあまりありません。
機械などはそのまま持っていても陳腐化していきます。
事業を中止し、別の事業に転換するとしても、工場を取り壊したり、機械を廃棄したりせざるを得ないでしょう。
工場や機械を転売、あるいは事業そのものを他社に転売することもありえますが、赤字事業ですから、やはり売却に際して損失は避けられないでしょう。
このように、事業の将来の見込みが立たなくなった時に、価値を生み出さなくなった資産を現実的な価値にまで落とすことを「減損」といいます。
(実際には、事業の見込み以外にも、土地のような資産そのものの時価が下がったり、物理的に資産がダメになってしまった場合も含まれます)
先のパナソニックの例では、激しい価格競争が続くTV事業から得られる儲けで、TV事業の資産の価値を将来も回収することができない、という評価になったものと考えられます。
減損は、工場の建物や機械などの実体のある資産(「有形固定資産」といいます)のほかにも、先に説明した「のれん」も対象にします。
前に多額の資金を投じて買収した事業から生じた「のれん」も、もしその事業から得られる儲けが低くなってしまったら、「のれん」の価値も低くなる、というわけです。
先のオリンパスの例では、買収はしたものの、そこから得られる儲けが当初の見込みよりだいぶ低くなってしまい、多額の「のれん」を回収できなくなってしまったのでしょう。
減損の会計は比較的新しい考え方です。日本では、多くの会社で平成17年4月から適用開始となりました。
それまでは、経営者は決算について、事業が黒字、赤字、ということだけ考えていればよかったかもしれません。
減損の会計導入後は、事業が赤字に陥ると、たちまち持っている資産そのものまで減損が必要となるケースも出てきて、赤字が増幅する傾向にあります。
常に儲け続けなければならない、いわば全力疾走を常に続けている経営環境にあるといえるでしょう。
「のれん」とは
Tweet前社長の解任問題でオリンパスが連日話題になっています。
前社長の解任は社内のコミュニケーションが問題とされたようですが、一方で前社長は過去に同社が行ったM&Aの価格が高すぎたことを問題視しているようです。
2011年10月20日付の日本経済新聞の報道によると、M&Aの買収価格が高すぎて、「のれん」について、「減損」を適用することになったことが書かれています。
さて、M&Aについて必ず出てくる言葉が「のれん」です。
「のれん」というと、飲食店の入り口に掛かっている、いわゆる「暖簾」を思い浮かべますが、M&Aに出てくる「のれん」とは一体なんでしょうか。
会社を買収しようとするとき、様々な方法で買収価格を決めます。
その価格の決め方は、理論的には色々な算定方法があります。
しかし、最終的には売り手と買い手の交渉ごとですから、最後は両者が折り合える金額で買収が成立することになります。
一方、その買収した会社は決算を行い、買収時点での財務諸表というものがあるはずです。
貸借対照表は、その時点での会社の財政状態を表します。
したがって、資産から負債を引いた純資産が、その時点での会社の財務諸表上の価値、ということになります。
ところが、この純資産で買収価格が決まる、ということはほとんどありません。
たいていは会社の資産価値を時価で再評価したり、その会社の事業の将来性を評価したりするので、買収価格は純資産よりも高くなります。
買収した会社は、親会社の財務諸表と一緒に連結することになるのですが、連結するときにこの再評価作業を行います。
しかし、資産や負債を再評価した後でも、どうしても差額が残ります。これを「のれん」といいます。
上に述べたように、その差額の主な内容は、事業の将来性を評価したりして出てくる金額です。その会社の事業の価値そのものといってもよいでしょう。
お店の「暖簾」がその店の価値そのものであるように、このような買収差額、つまり資産などを再評価しても残る事業の価値を「のれん」と呼ぶわけです。
図を見てみましょう。
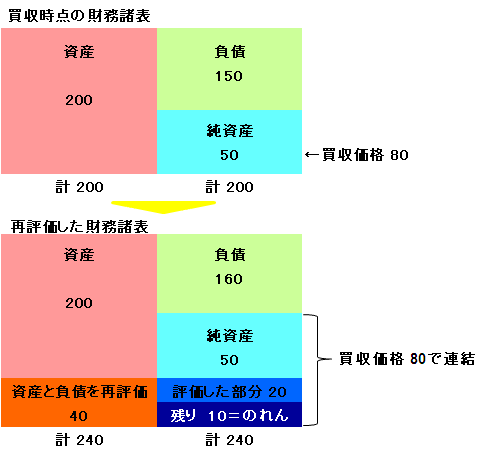
買収時点での純資産が50となっている会社を買収価格80で買収したとします。
資産や負債を再評価した結果、純資産は20増えたとしましょう。
それでも、買収価格80-再評価20-純資産50=10が残ってしまいます。これが「のれん」というわけです。
ところで、純資産よりも低い価格で買収することもあります。そうすると「のれん」はマイナスになります。これを「負ののれん」といいます。
赤字が続いて誰も買い手がつかなくなってしまった会社に目をつけて、安く買って、親会社のノウハウを上手く移転しながら会社の持っている潜在価値を引き出す。
そういう時に「負ののれん」が発生することがあります。
次回「減損とは」に続く
金融担当大臣、IFRS強制適用延期
Tweet6月21日、金融担当大臣より、IFRSの2015年3月期強制適用は考えておらず、仮に強制適用する場合であっても、決定から5-7年程度の十分な準備期間の設定を行うとするなどの談話が発表されました。
そうすると、仮にあと数ヶ月以内に強制適用を決定したとしても、5-7年の準備期間を考慮すれば、強制適用は早くて2016年3月期、ということになります。
その理由としては、同等性の評価のほか、東日本大震災の影響もあるとされています。
IFRSの導入は検討すべきことも多く、それなりの負担もあるため、大震災の影響を考えますと2015年からの強制適用は現実的に難しい面もあるでしょう。
しかしながら、国際社会において今の日本の置かれた状況をみますと、延期はしても適用の見直しはすべきではないと考えます。
IFRSの導入は産業界を中心に反対が多いと聞きます。確かに、今までの日本の基準とは異なる部分もあり、企業によっては今の財政状態が大きく変わってしまう、というところもあるでしょう。
現在の日本の基準は一昔前に比べるとかなりIFRSに近付いています。IFRSの強制適用とは別に、これからも少しずつ国際社会の潮流に合わせた変更は行われていくものと考えられます。
また、IFRSを導入する/しないという、それ自体が企業の本当の実態を変えてしまうわけではありません。
そもそも、会計基準というものは、企業の実態を測るモノサシに過ぎません。
たとえば、反対意見の焦点の一つである時価主義も、仮に時価主義を導入しなかったとしても、企業が持っている資産や負債そのものが持っている価値とその下落リスクがなくなってしまうわけではなく、財務諸表に表れてこない、というだけに過ぎないのです。
会計基準の違いの背後には、理論的背景やその社会のもつ文化的背景なども左右しますが、現代のように企業が様々な形で国際社会と関わりを持つ時代では、すべての企業が同じ基準で測定され、同じ土俵に乗る、ということが必要と思われます。
震災と前後して、既に”日本パッシング”が始まりつつあることも気になる点の一つです。
天然資源に乏しく、かつ国内市場も成熟期を迎えつつある我が国は、国際社会との関わりなしに存立できません。
その中で、我が国の企業が独特の会計慣行の下で作られた財務諸表に寄っているということは、今後の日本の企業活動の道を狭めてしまうことを筆者は恐れます。
国際資本市場で資金調達しない会社にまで強制適用すべきでない、という意見もありますが、全ての企業は何らかの形で他人資本に頼っており、その資本の出し手の裏にはさらに別の資本があって、今日のような複雑な資本市場では、間接的には世界中が資本家、とも言えます。
日本が独特の会計慣行の下に留まるとすると、日本を嫌忌する資本家が流出し、それはひいては、国内資本(と思っているもの)の減少につながることもありえます。
今回の談話は、単に震災の影響から導入を延期している現実的対応としてであって、国際潮流の中で日本が取り残されないよう、引き続き国際化の検討を進めてほしいと筆者は考えます。